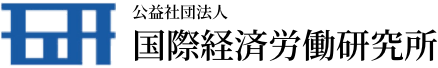機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2025年10月号(通巻1154号) 特集概要
2025春闘
成果と今後の課題(後編)
Contents
春闘と非正規労働者の賃金
― 人手不足と最低賃金上昇にどのように対応するのか
金井 郁(埼玉大学 人文社会科学研究科 教授)
「2025春季生活闘争」を振り返って
仁平 章(日本労働組合総連合会(連合)総合政策推進局長)
産別組織インタビュー
西尾多聞 氏(UAゼンセン 書記長)
橋本修平 氏(電機連合 事務局長)
過去の「春闘特集」寄稿論文一覧
本誌では、毎年定例的に春季生活闘争(以下、春闘)の成果と今後の課題を特集している。特集は本号および前号(9 月号)の2 号にわたって掲載しており、本号はその後編である。
特集1 は、金井郁氏(埼玉大学大学院人文社会科学研究科 教授)より、「春闘と非正規労働者の賃金――人手不足と最低賃金上昇にどのように対応するのか」と題して、ご執筆いただいた。2025 年春闘の結果と昨今のマクロ経済環境の変化を踏まえた上で、スーパーマーケット業の労働組合の春闘交渉を事例に、賃金交渉がどのように行われているのか、また、それが非正規労働者の賃金や賃金制度にどのように影響を及ぼしているのか検討していただいている。事例からは、正社員とパートタイマーに同じように「定期昇給」の考え方が適用され、実際に正社員の新人層とパートタイマーのベテラン層の賃金水準に差がなくなってきていることなどを明らかにしている。事例を踏まえ、近年のマクロ経済環境を背景とした春闘の動向によって、非正規社員率を高めるというこれまでのチェーンストア業界の戦略に変化を促し、公正な賃金制度を構築することが、生き残り戦略の一つとなるとしている。
特集2は、仁平章氏(連合・総合政策推進局長)による寄稿である。連合の2025 春季生活闘争のまとめ(7 月17 日発表)を踏まえ、今次闘争の特徴、取り組みの結果、評価と課題についてご寄稿いただいている。今年の特徴は、賃上げのすそ野を社会全体に広げ働く仲間「みんな」の生活向上をめざすこと、「賃金も物価も上がらない」という社会的規範を変えることの2点であった。賃金・経済・物価を安定した巡航軌道に乗せる正念場であるという認識の下、取り組まれた今次春闘は、2年連続で定昇込み5%台の賃上げが実現し、賃上げ分は過年度物価上昇率を上回っており、新しいステージの定着に向け前進したと評価している。
特集3 の産業別労働組合へのインタビューでは、今年はUA ゼンセン、電機連合、JAM、生保労連、サービス連合の5 組織(略称、組織規模順)にご協力いただいた。本号にはUA ゼンセンと電機連合を掲載している。UA ゼンセンは、2025 闘争では「早く、高く、そして広い」相場形成を意識して共闘を進め、賃上げにおいてその効果が確認されていることが特筆される。また、日本におけるパートタイマーの約8割がUAゼンセンに加入しているため、パートタイマーの賃上げも含め、労使の交渉を基本としつつ、今後の闘争のあり方を考える必要性についても言及している。インタビューの最後にはUA ゼンセンの「運動の基本」における賃金に関する考え方もご紹介いただいている。電機連合は、中闘(大手)労組では1 万2000 円以上
の賃金引上げを獲得し、高水準の妥結となった。また、2023 闘争以降進めてきた、産業別最低賃金(18 歳見合い)の水準を高卒初任給の水準に準拠させていく取り組みについても実現がはかられている。今年は労働協約の改訂年ではなかったものの、近年力を入れて取り組まれている、障がい児等を養育する労働者の個別事情を踏まえた取り組み、労働時間の削減や柔軟な働き方についてもお話をうかがっている。
本特集にあたって、ご協力いただいた皆様に感謝申し上げます。