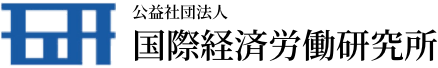機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2021年10月号(通巻1114号)特集概要
大人の発達障害
―職場におけるダイバーシティーを考える―
Contents
発達障害と就労をめぐる現状と課題
梅永 雄二(早稲田大学 教育・総合科学学術院 教育心理学専修 教授)
大人のADHDと認知行動療法の実践
中島 美鈴(九州大学人間環境学研究院 / 肥前精神医療センター)
近年、「発達障害」という言葉がテレビや新聞、SNSなどで取り上げられる機会が増え、世間に広く知られるようになった。このような背景もあり、子どものみならず、大人の発達障害にも関心が高まっている。
そこで本号では、「大人の発達障害」をテーマとし、就労にかかわる観点に焦点を当て、発達障害と就労をめぐる現状や課題の把握、発達障害を抱える当事者も周囲も働きやすくするためにはどうすればいいのか、などについて、専門家から寄稿いただいた。
特集1は、梅永雄二氏(早稲田大学教育・総合科学学術院 教育心理学専修 教授)に、「発達障害と就労をめぐる現状と課題」と題して執筆いただいた。本稿では、発達障害者の雇用に関する現状と課題、職場での対応策(適切なジョブマッチングや合理的配慮)、周囲が配慮するべき点についてまとめられている。また、労働組合に向けての提言も触れていただいている。
特集2は、「大人のADHDと認知行動療法の実践」として、中島美鈴氏(九州大学人間環境学研究院/肥前精神医療センター)に執筆いただいた。本稿では、大人の発達障害を抱える人が職場で直面する課題、認知行動療法の実践例等について紹介いただいている。
上述のとおり、本号の特集では、「働く」という場面での具体的な課題や対応策が中心であるが、ダイバーシティの観点からも、注目すべきテーマだと考えられる。産業界では「ニューロダイバーシティ」という言葉が聞かれるようになった。「ニューロダイバーシティ」とは、発達障害を能力の欠如や優劣として捉えるのではなく、脳や神経に由来する個人レベルでの様々な特性の違いと捉えて相互に尊重し、その多様性を社会資産として評価する考え方で、ダイバーシティ(多様性)の概念を人の精神活動に適用したものである(注1)。海外の大手企業では独のSAPや米のヒューレット・パッカードエンタープライズ(HPE)などが先鞭をつけ、特にソフトウエア開発を主事業とする企業において取り組みが進んでいる。日本では、IT分野のほか、アクサ生命によるニューロダイバーシティの概念の社内外への啓発活動開始(2020年4月)、武田薬品株式会社の「ニューロダイバーシティ推進プロジェクト」(2021年4月)などがみられる。この「ニューロダイバーシティ」は、今後、働くことを考える上での重要な一視点ではないかと考えられる。
本誌ではこれまで、ダイバーシティの観点から様々な特集を企画してきた。直近では、2019年5・6月合併号において、「ダイバーシティの実現に向けて」と題し、合理的配慮、性の多様性、労働組合の取り組み等を掲載している(注2)。今後も、働くこととダイバーシティの観点から、様々なテーマを取り上げていくことができればと考えている。
(注1) 武田薬品株式会社「『大人の発達障害NAVI』ウェブサイト公開について」
https://www.takeda.com/ja-jp/announcements/2021/otona-hattatsu-navi/(2021年11月10日閲覧)
(注2) 掲載した内容は以下の通り。
特集1 多様な人たちが力を発揮できる職場へ ~合理的配慮を通じて~
松波 めぐみ ((公財)世界人権問題研究センター 研究員)
特集2 性の多様性をめぐる国内外の動向
東 優子 (大阪府立大学大学院人間社会システム科学研究科 教授)
特集3 インタビュー 労働組合におけるダイバーシティの取り組み
コニカミノルタ労働組合