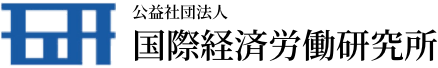機関誌Int
’
lecowk
巻頭言 「国 宝」
(公社)国際経済労働研究所 会長 古賀 伸明
映画「国宝」が大きな話題を呼んだ。私も複数の知人からの勧めで、映画館に足を運んだ。
公開直後から劇場は満員の盛況で、観客が「忘れられない体験だった」と語るのは、この作品が単なる娯楽を超えて、日本の伝統と人間の生き方に深く関わっているからだろう。
日本における「国宝」とは、文化財保護法により特に重要と認定された建築や美術品を指す。しかし一方で「人間国宝」と呼ばれる人々がいる。正式には「重要無形文化財保持者」とされ、伝統芸能や工芸における高度な技能を体現し、継承する使命を担う。歌舞伎俳優や能楽師など、個人が文化財とされる存在だ。映画「国宝」は、まさに一人の青年が歌舞伎の世界で生き抜き、人間国宝に至るまでを描いた約 3 時間にわたる壮大な物語である。
その舞台である歌舞伎は江戸時代初期に誕生し、約400 年の歴史を重ねた日本独自の演劇芸術だ。豪華な衣装や化粧、花道、見得などの様式美、浄瑠璃や下座音楽による独特の音響。舞台と観客が一体となるその芸は、2008 年にユネスコ無形文化遺産にも登録された。
映画の主人公・立花喜久雄は、任侠の家に生まれながら、父親の組長が組同士の抗争で死亡し、歌舞伎の家に引き取られるという運命を背負う。血筋と無縁であった少年が修行を重ね、やがて人間国宝に至る過程には、華やかな舞台の裏にある厳しい稽古や犠牲、師や仲間との葛藤が描かれる。観客は半世紀にわたる人生の軌跡を追体験し、ただの傍観者ではなく人生の同伴者となる。
この映画が評判を呼ぶ理由の第一は、制作陣と俳優陣の力だ。監督は「フラガール」の李相日、脚本は奥寺佐渡子、美術は世界的評価を受ける種田陽平。主演の吉沢亮に加え、横浜流星、渡辺謙、寺島しのぶ、永瀬正敏らが出演し、歌舞伎の所作を徹底的に再現しながら映画ならではの映像的ダイナミズムを実現した。
第二に、物語が普遍的なテーマを持つからだ。才能とは何か、血筋と努力の関係、芸の道の果てにある幸福や孤独。ライバル俊介との関係は「比較」と「嫉妬」という人間の根源的問題を映し出す。歌舞伎を知らぬ観客も、自分の人生に引き寄せて共鳴できる。
第三に、舞台裏の厳しさを描いたことだ。華やかさの陰にある過酷な修行や裏方の支えを、原作者の芥川賞作家・吉田修一の黒衣としての体験に基づくリアルな描写で示す。観客は美の背後にある献身を理解し、深い感動を得る。
見どころは多い。修行時代の緊張感、初舞台の震え、ライバルとの別離、大舞台での圧倒的演技。所作は単なる模倣でなく、生身の感情と伝統が融合し、虚構を超えた真実を生む。映画館という空間でしか味わえない迫力がある。
本作が観客に突き付けるのは「伝統と個人」の関係である。歌舞伎は血筋を重んじる一方、偶然入り込んだ者も芸を極め得る。人は伝統に縛られながらも、伝統を更新する主体でもある。喜久雄の人生は宿命と自由の葛藤を体現し、観客に「自分はどう生きるか」という問いを投げかける。
さらに「芸の道とは何か」という問いも重要だ。芸は単なる娯楽や仕事ではなく、一生をかけた修行であり、心を豊かにする営みだ。これはスポーツや学問、仕事など全ての分野に通じる普遍性を持つ。観客は「自分にとっての芸は何か」と考えずにいられない。「国宝」はこうして、日本人が自らの文化と生き方を見つめ直すきっかけとなる。
文化は保存ではなく継承と変化の中に生きる。映画はその姿を映し出す。異なる血を持つ青年が伝統に身を投じ、新しい歌舞伎を創り、人間国宝と呼ばれるに至る。これは伝統の柔軟さと生命力の証である。
映画を見た人々が実際に歌舞伎を鑑賞したくなるかもしれないし、自らの仕事や趣味を「小さな芸」として振り返るきっかけになるかもしれない。芸術は誰もが自分の生活の中で追い求められる。そうした普遍的気づきを与えることが、この映画の最大の功績だ。
この原稿を書いている時、「国宝」が来年の米アカデミー賞国際長編映画賞の対象となる日本代表作品に選ばれ、米国での放映も決まったという報道が流れた。
2025.11