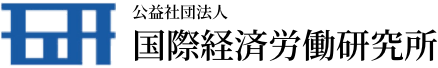機関誌Int
’
lecowk
巻頭言 令和の米騒動
(公社)国際経済労働研究所 会長 古賀 伸明
誰が称したのか、「令和の米騒動」。2024年に5㎏2200円だったコメが25年1月には4000円を超え、備蓄米の放出で平均単価は下がったが状況は変わらない。確かに年々米離れが進み、1人の1年間のコメの消費量は、1962年の約118㎏から現在は約50㎏と半減している。とはいえ、コメの価格高騰は物価高に悩む消費者に打撃を与え、飲食業界や給食制度にも影響を及ぼすと共に、生産者や流通業者にとっても大きな課題となっている。
この現象は、異常気象による作況不良、肥料や燃料の価格上昇、輸送コストの増加、さらには国際情勢なども含めた複合的な要因が重なった結果だが、その根底には日本の農業政策の行き詰まりがある。
日本農業が抱える構造的課題は多岐にわたる。まず、農業従事者の高齢化が深刻だ。平均年齢はすでに67歳を超えており、70歳以上の稲作農家が60%を占め、若い世代の新規就農は限定的だ。後継者不足は深刻で、耕作放棄地の増加が農地の荒廃と生産力の低下を招いている。所得を安定させ、その上で農家のやる気を引き出す魅力あるコメ農政へと転換して行くことが必要になる。
また、長年続いてきた価格維持や生産調整に依存した政策は、農家の自立や経営の創意工夫を妨げ、経営の革新が進まない原因ともなっている。加えて、都市と農村の分断が進み、消費者が農業や食の現場を知る機会が減少しており、これが地産地消やフードロスの問題にもつながっている。
さらに、多くの事業者が介在する複雑な流通構造にも課題がある。当初放出された備蓄米は、店頭に並ぶまで時間がかかった。何が障害だったのか、検証が急がれる。
こうした状況を打開するには、日本の農業の持続可能性、国際競争力、そして食料安全保障などを見据えた農業政策の根本的な転換が求められている。
まずは、農地の集積・集約を進め、農業の規模拡大と法人化を促進することが不可欠だ。あわせて、スマート農業の導入支援を通じて、労働力不足の解消と経営効率の向上を図るべきだ。もちろん、中間山地の斜面に水田が作られている日本の地形的特質を鑑みれば、すべてを集約し大規模化することは難しい。前向きな小規模農家を守ることは、農業を守るだけでなく、治水機能や環境を守ることにもつながることも忘れてはならない。
一方では、いわゆる減反政策から脱却し、市場ニーズに基づいた柔軟で多様な経営支援策に転換することが求められる。特に、有機農産物や輸出向けの高付加価値作物などの育成に注力することで、農家の収益性と選択肢を広げる必要がある。
地域資源を活かした6次産業化の推進も、農業の持続可能性を高めるうえで重要だ。生産・加工・販売を一体とするビジネスモデルは、地域経済に新たな雇用を生み出し、地方の活性化にも寄与する。また、農業への新規参入を促すには、若者や女性に対する初期投資支援、生活支援、研修制度の整備が欠かせない。農業教育や食育の強化を通じて、将来の担い手の育成にもつなげるべきだ。
さらに、世界的な食料供給の不安定化が進む中で、食料自給率の向上は国家安全保障の観点からも重要だ。特にコメ、小麦、大豆などの基幹作物については、戦略的な備蓄体制や生産基盤の整備が必要となる。
農業政策の実行にあたっては、農協の役割の再構築も求められる。従来の組織構造や業務のあり方を見直し、販売・流通の効率化、デジタル化、地域との連携強化などを進めていくことが望まれる。また、都市と農村をつなぐ取り組みとして、都市農業や市民農園の整備を進め、消費者が農業に関心を持ち、関与する仕組みづくりが重要だ。
農業は単なる生産・消費活動ということだけでなく、日本の文化、自然環境、地域社会を支える重要な基盤だ。持続可能で魅力ある農業を再構築することは、日本社会全体にとっての課題であり、未来への投資でもある。今こそ、時代に即した大胆かつ柔軟な政策転換が求められており、既存の枠組みにとらわれず、未来を見据えた改革を強く期待したい。
2025.9