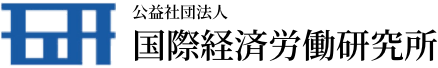機関誌Int
’
lecowk
巻頭言 「ラ・カンパネラ」
(公社)国際経済労働研究所 会長 古賀 伸明
2024年4月、世界的ピアニスト、フジコ・ヘミングが92歳でその生涯を閉じたという知らせが届いた時、彼女の「ラ・カンパネラ」の音の軌跡に思いを馳せた。
「ラ・カンパネラ(LaCampanella)」は、フランツ・リストがヴァイオリニスト、ニコロ・パガニーニの主題に基づいて作曲した「パガニーニによる大練習曲」の第3番だ。その原題はイタリア語で「鐘」。パガニーニが使っていたヴァイオリンの高音域を、ピアノで模倣するような技巧を極限まで追い込みながらも、旋律の中に抒情を編み込むことで、単なる技巧の誇示にとどまらない、人の情念をゆさぶる音楽を生み出した。軽やかな指の跳躍が鐘の音を模し、華麗でありながらもどこか哀しみを含んだ旋律は、多くの人々の心を捉えて離さない。
この「ラ・カンパネラ」を20世紀末に世界中の人々に改めて届けたのが、日本人ピアニスト、フジコ・ヘミングである。スウェーデン人と日本人のハーフとして生まれ、音楽一家に育ち、早くからその才能を認められながらも、幾度もの不運に見舞われた彼女。留学先のヨーロッパで演奏活動を軌道に乗せつつあった矢先、難聴という試練が訪れる。聴力を失い、そして貧困と孤独に沈みながらも、彼女は音楽を諦めなかった。
1999年、日本のテレビ番組で彼女の特集が放送された夜、彼女の演奏、特に「ラ・カンパネラ」の美しさと情熱に、多くの視聴者が涙した。音楽は技術ではなく魂なのだと、フジコの姿がそれを証明していた。発売されたCDは異例の大ヒットとなり、彼女は還暦を過ぎてから世界的なピアニストとして脚光を浴びた。
このフジコの「ラ・カンパネラ」に心を奪われた一人に、佐賀県の海苔漁師がいた。名前は徳永義明。長年、有明海と向き合いながら、家族を養ってきた彼は、クラシック音楽にはまるで縁のない人生を歩んでいた。しかし、テレビで見たフジコの演奏に衝撃を受けた。彼女のピアノから流れ出る「ラ・カンパネラ」の音は、まるで過去の記憶や、言葉にならなかった感情を呼び覚ますかのようだった。
それから徳永さんは、独学でピアノを始める。年齢は50を過ぎていた。海の仕事が終わった夜に、ひとり鍵盤に向かう日々が続いた。譜面も読めなかったが、何度も何度もCDを聴いては、音をたどり、ひとつずつ鍵盤の場所を確かめた。海で鍛えた手は、ピアノには向いていないと人は言ったが、徳永さんは一切諦めなかった。
その情熱と粘り強さはやがて周囲の人々を動かし、メディアで紹介されるようになり、そして運命は再び巡る。なんと徳永さんは、ついにフジコ・ヘミング本人に認められ、彼女のコンサートの前座として演奏するという夢のような舞台に立つことになったのだ。
その姿は、多くの人に「遅すぎる挑戦などない」という勇気を与えた。手探りでピアノを学び、何年もかけてようやく弾けるようになった「ラ・カンパネラ」。徳永さんの演奏は、決して完璧なテクニックではなかったかもしれない。しかし、彼の音にもまた、人生の風と波の音が、そして深い人間味が滲んでいた。
徳永さんの挑戦の物語は、地元有志の働きかけによって、今年1月に映画化(主演)・伊原剛志)された。映画「ら・かんぱねら」は、観客の涙を誘い、地元の映画館で反響を呼び、全国に広がった。そこには、ただの「感動物語」ではなく、人が音楽に導かれ、自らの人生を再び紡ぎなおすという、リアルで力強い人間ドラマがあった。私が観た映画館では、映画が終わると客席から大きな拍手が沸き起こった。
フジコ・ヘミングと徳永義明。まったく異なる道を歩んできた二人が、「ラ・カンパネラ」という一つの曲で結ばれたことは、音楽の持つ不思議な力をまざまざと感じさせる。リストが遥か昔に作った「鐘の音」は、パガニーニの魂を引き継ぎ、フジコの指先を通り、海苔漁師の徳永さんにまで届いた。徳永さんの手が奏でる「ラ・カンパネラ」は、荒波を越えて生き抜いてきた人生の証だった。その鐘の音は、希望の鐘、挑戦の鐘、そして再生の鐘だ。今も、誰かの心を打ち続けている。
2025.8