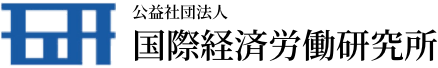機関誌Int
’
lecowk
巻頭言 代名詞は「知的創造理論」
(公社)国際経済労働研究所 会長 古賀 伸明
雑然となった書棚を整理していると、奥の方に『失敗の本質』の背表紙が見え手に取る。1984年に戦史研究者と組織論研究者、両者の共同研究において生まれた書籍だ。その研究会を主導したのが、野中郁次郎氏であり、今年1月27日に89年の生涯を閉じた。
『失敗の本質』は、旧日本軍の組織的失敗を分析した名著として広く読まれている。それは単なる軍事的・戦略的な失敗ではなく、日本軍の「組織文化」「意思決定の問題」「情報共有の欠如」など、現代の企業経営や組織運営にも通じる示唆を多く持っているからだ。時代を超えて、組織が陥る共通の問題を鋭く指摘した本書は、今後も多くの人に読み継がれるだろう。
野中氏の代名詞のようになっているのが「知的創造理論(SECIモデル)」だ。そのキーワードは「暗黙知」と「形式知」であり、個人が持つ知識や経験を「暗黙知」と呼び、組織で共有できる形になった知識や経験を「形式知」と呼んだ。SECIモデルでは、暗黙知が形式知に変換されて経営に活かされるためには、共同化(S)、表出化(E)、連結化(C)、内面化(I)の4つのプロセスを定式化し、これらを絶えず繰り返すことでさらに新たで高度な知が創造されるとする。
このモデルは、欧米の研究者にも影響を与え、多くの企業や組織で取り入れられた。もう20数年前の大阪での講演会で、SECIモデルの循環図を示して「この紙切れ1枚のために、私は何十年も研究してきました」といって、会場を沸かせたことを思い出す。
日本企業は「失われた30年」から脱出できず、その原因を野中氏に尋ねたインタビュー記事を読んだ。「行き過ぎた分析主義。何事にも理論ありきで、“オーバーアナリシス(分析)”“オーバープラニング(計画)”“オーバーコンプライアンス(順守)”に陥っている。過度な可視化と定量管理を課された現場は失敗を恐れ、挑戦しなくなる。数値経営に振り回され、日常が数字化しすぎているのは危機的状態だ。これでは人間の“野性”やクリエイティビティは劣化する」「かつての日本的経営の良さは、未来に向けた筋書きを共有、従業員一人ひとりがリーダーシップを発揮し、自律分散的に試行錯誤しつつ前進していくことにあった。人間の野性味から出る創造性、臨機応変に決断・実行する実践的知恵が劣化している」と述べている。
そんな思いからか、2022年4月には『野生の経営』を出版。人間が本来持つ「野性」を、身体感覚や直観力、感性といった要素を含む“生きた知恵”と定義し、「我々がかつてやってきたことは、もっと野性的だった。まず、やろうじゃないかから始まっていたはず。しかし、今は身体ではなく、先に頭が来すぎていると思う」「イノベーションの源泉は大体、最初に理論ありきというより、何をやりたい、という思いありきなのだ」と。
最後の著書は『二項動態経営』だ。その「まえがき」は「経営とは何か、と聞かれたら、迷わず“生き方”だと答えるだろう。経営は、人間の営為そのものであり、そこに関わる人間の生き方が色濃く投影される」から始まる。
そして、経営活動において直面するさまざまな矛盾やジレンマを「あれかこれか」の二項対立で切り抜けるのではなく、苦しくても「あれもこれも」の二項動態を実践し、新たな価値を創造することこそが、過去の自己を超えていくただ一つの道と説く。
4月には追悼セミナーが開催され、関係者が思い出やご功績を語り合った。私もオンラインで視聴させていただいた。
経営学の枠を超え根底には「人間とは何か」、根幹には「本質」を追求する哲学があった。このような根源的な問いに向き合い続け、思想家ともいえる野中氏に、何度かお会いするチャンスはあったが、どうしても日程が合わず実現しなかった。極めて残念でならない。改めて、心よりご冥福をお祈りする。
合 掌
2025.7