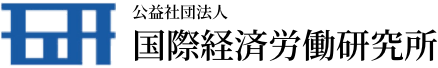機関誌Int
’
lecowk
地球儀 国民に「1 億総中流」を思い込ませた「世論調査」
(公社)国際経済労働研究所 所長 本山 美彦
2001年の省庁再編成前の厚生省は、1953~65年まで「厚生行政基礎調査」を実施していた。これは、きちんとしたデータに基づく本物の調査であった。被保護世帯の平均消費支出額に満たない消費額であった世帯(低消費世帯)の割合を実際に調べたものであった。まさに「働く貧困層」(ワーキングプア)の割合を示す数値であった、しかし、貧困を示すこうした数値は、1966年に中断された後、2009年まで作成されることがなかった(https://www.hinkonstat.net/日本の貧困/1-歴史/)。
政府は、それに代えて、内閣府の「国民生活に関する世論調査」を利用してきた。この世論調査は、1945年から不定期に行われていたが、自らを中流のランクにいるだろうと思っている国民の意識を利用すれば、国民を政府側に引き寄せることができると意図したのであろう。
第1回の世論調査によると、生活の程度に対する回答比率は、「上」0.2%、「中の上」3.4%、「中の中」37.0%、「中の下」32.0%、「下」17.0%であった。自らの生活程度を「中流」とした者、すなわち、「中の上」「中の中」「中の下」を合わせた回答比率は70%を超えていた(現実には多くが貧困世帯だったのに)。1960年代半ばには、80%を超え、「所得倍増計画」の下で日本の「国民総生産」(GDP)が世界第2位となった1968年を経て、1970年以降は約90%となった。そうした数値を根拠に、1979年の『国民生活白書』では、国民の中流意識が定着したと高らかに宣言されたのである。
こうして、「一億総中流」意識に国民は染められた(https://ja.wikipedia.org/wiki/)。
政府が、厚生労働省を通じて、世帯所得統計の中央値の半分に満たない所得層を「相対的貧困世帯」として公表したのは、やっと2009年になってからである(https://www.hinkonstat.net/日本の貧困/1-歴史/)。
「ワーキングプア」という言葉は、社会学者の江口英一による造語であり、その言葉を用いた番組が2006年にNHKで放映された。
「いま、日本では、<ワーキングプア>と呼ばれる<働く貧困層>が急激に拡大している。ワーキングプアとは、働いているのに生活保護水準以下の暮らししかできない人たちだ。生活保護水準以下で暮らす家庭は、日本の全世帯のおよそ10分の1、400万世帯とも、それ以上とも言われている」(NHKスペシャル「ワーキングプア~働いても働いても豊かになれない~」。https://www.nhk.or.jp/special/detail/20060723.html)。
メディアが、政府を反省させた。NHKの大きな貢献であった。
2025.8