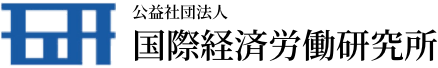機関誌Int
’
lecowk
地球儀 5回も通貨が変更になった沖縄
(公社)国際経済労働研究所 所長 本山 美彦
2022年5月15日は、沖縄の本土復帰50周年に当たる。ウクライナ情勢が日増しに緊迫したものになっている今日、沖縄の地政学的な重要性に注目が集まっている。日本国憲法の改定論者にとって、現在を最高の好機と見ているのだろう。
今回は、これまであまり議論されてこなかった沖縄の通貨問題について語りたい。
米軍が沖縄本島に軍政府を樹立した1945年4月1日から翌年の4月15日まで、沖縄では旧日本銀行券がわずかながら流通していた。しかし、余儀なく収容所生活をしていたほとんどの住民は、物々交換で飢えをしのいでいた。
そして、1946年4月15日、米軍基地周辺に限定された形で、B型軍票紙幣(B円)が発行された(第1回目の通貨変更)が、そのわずか4か月後の同年8月5日、B円を廃止して、新日本銀行券(新日本円)に切り替えるとの方針が示された(実施は同年9月1日、第2回目の変更)。理由はいまだ不明である。おそらく米軍政府は通貨政策に迷っていたのだろう。しかし、本土からの引揚者たちが持ち込んだ新日本円が、物資不足の沖縄に深刻な物価高騰をもたらした。
そのこともあって、軍政府は1947年にB円を復活させ、翌48年にB円を唯一の法定通貨に仕立てた(第3回目)。これは、1ドル=120B円というB円高の交換レートで、物資不足に悩む沖縄救済の輸入促進策であった。新日本円はすべて回収された。ちなみに当時の日本の外貨準備の約3分の1は、本土から沖縄への輸出で稼ぎ出されたものである(1ドル=360円の円安)。
1958年9月15日、外資導入を活発にさせるために、B円の米ドルへの全面切替が開始された(第4回目)。しかし、効果は上がらなかった。軍政府と言えども、本国のドルは、B円のように勝手に増発できるものではない。ドルの入手は日米政府による財政援助に頼るしかなかった。こうして、米軍基地に依存する経済体制が強化された。
そして、本土復帰によって、ドルから日本円が法定通貨になった(第5回目)。ドル・円レートは本土よりも沖縄の方が円に不利であった(『女性自身』2019年8月15日号の電子版記事を参照した)。
金融論全盛の時代なのに、沖縄の通貨問題を軽視してきたこれまでの研究史を哀しく思う。
2022.5/6