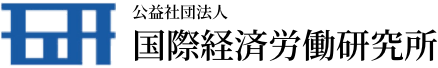機関誌Int
’
lecowk
Int'lecowk 2025年7月号(通巻1151号) 特集概要
「21世紀型成熟社会の理論」
研究プロジェクト完了に寄せて
Contents
社会運動ユニオニズムの歴史的意義と今日的課題
―アメリカ労働運動を事例として―
新川 敏光
1. 研究プロジェクトの概要
当研究所では、2022年から2年間にわたり、「21世紀型成熟社会の理論」研究プロジェクト(以下、本プロジェクト)を開催した。本プロジェクトは、社会政策・労働政策の理論的・思想的基礎について理解を深め、労働組合(運動)の政策形成・発信力を高めることを目指して行われたものである。研究体制、参加組織は以下の通りである。
■研究体制
新川 敏光 氏(法政大学教授・京都大学名誉教授、当研究所理事)主査
水島 治郎 氏(千葉大学教授)、諸富 徹 氏(京都大学教授)、山崎 望 氏(中央大学教授)
※ 所属、役職は本プロジェクト終了時のもの。
■参加組織
UAゼンセン、自動車総連、電機連合、JAM、基幹労連、生保労連、JP労組、情報労連、フード連合、サービス連合、日放労
※ 二期のうち前期のみ参加の組織を含む。略称表記。本プロジェクトでは、大きく2点の問題意識にもとづき、各回でテーマを設定し、各回のテーマに関連する分野の専門家を講師に招いて、講演および議論・意見交換を行った。
・問題意識1―現代社会の現状と変容への理解
近代社会においてはほぼ自明視されてきた経済成長が多くの先進国において鈍化している。それは福祉国家の基礎を揺るがし、その結果として代表制民主主義の正統性にも疑義が呈されるようになる――いわゆる「成熟社会論」が描く現代社会の一側面はこのようなものである(成熟社会と言う場合の「成熟」は「(経済)成長の先」という程度の意味で使われており、肯定的なニュアンスをつねに含むものではない)。このように20 世紀の社会が「当たり前」と見なしてきた政治や経済の体制が揺らぐ現状にあって、私たちは「いま自分たちがどのような社会に生きているのか」という現状認識や、「これから社会はどのような方向に進んでいくのか」という将来の見通しを、十分にはっきりと持てないでいる。「資本主義の終焉」や「民主主義の危機」といったテーマを扱う書籍がしばしば大きなセールスを記録するのも、こうした現状と先行きの見えにくさ(それゆえの、現状や先行きを理解する手がかりを得たいという願望)を物語っているのかもしれない。
このような状況において今後の運動論を考えようとするならば、政治の面では代表制民主主義の正統性、経済の領域ではグローバル化以降の資本主義の展開、社会という領域では社会運動の変容(いわゆる「新しい社会運動」の登場など)といったように、現代社会のさまざまな領域において、近代社会の何が問い直されているのかを知ることがまずもって重要であると考えられる。「何が問題なのか」を理解することによってこそ、現代社会にアジャストした運動を考えることができるようになるはずだからである。
・問題意識2-現代社会における労働組合・労働運動の役割の再考
20 世紀の社会において、政党との関係の有無に関わらず、働く者の生活を守るための政策・制度を立案し要求する社会運動を通じて、労働組合は世界各国において固有の立ち位置を占め、社会的な問題にコミットしてきたと言える。しかし、運動が上述のような社会変容にアジャストできなければ、運動が社会から十分な訴求力をもって受けとめられることも難しくなると考えられる。経済成長の先にある現代社会の状況を認識した上で、広く社会を視野に入れた運動のビジョンと労働組合の社会的役割を再定義すること、またそのビジョンのもとで新たな連帯を創り出していくことが、運動にたいする社会的な支持と持続可能性のために重要であると考えられる。本研究プロジェクトは、そのような再定義に向けた論議がさまざまな組織のなかで・あいだで進展するためのきっかけや論点を提示するプラットフォームとして企画された。
各回の講演内容と講師は以下のとおりである。取り上げられるテーマは多様であり、特定分野の制度や活動を扱う回から理論的な議論を中心とする回まで、抽象度の程度もさまざまである。本研究の趣旨からすれば、政治や経済、「社会全体」をマクロな観点から抽象的に語る「大きな理論」こそ重要である、という印象を持たれる読者もあるかもしれないが、それは必ずしも正しくない。理論をもつことはもちろん重要であるが、具体的な現実との対話を通じてそのような理論の妥当性を検討し、ボトムアップで見直していくという批判的な作業なくしては、現実の理解も頑健なビジョンの構築も望み得ないからである。民主主義や資本主義を語る一見したところ美しい「大きな理論」が、その盲点のうちにさまざまな抑圧や排除を含みかねないということを、歴史は教えている。そのような観点から見るとき、テーマと抽象度のばらつきはむしろ本研究プロジェクトにとって重要な要素であった。
| 開催日 | 講演タイトル | 講師(敬称略) |
| 第1回 2022年10月3日 | 研究会発足基調報告 |
新川 敏光 |
| 第2回 2023年3月1日 | 資本主義、気候変動、 |
諸富 徹 |
| 第3回 2023年5月1日 | 社会運動への視点から |
富永 京子 |
| 第4回 2023年8月29日 | 貧困の現場から社会を変える |
稲葉 剛 |
| 第5回 2024年1月23日 | 公正な社会とは何か |
神島 裕子 |
| 第6回 2024年6月14日 | 現代日本における |
髙谷 幸 |
| 第7回 2024年9月11日 | 2024年アメリカ大統領選挙と |
西山 隆行 |
| 第8回 2024年11月1日 | デモクラシーの行方① デモクラシーの行方② |
山崎 望 水島 治郎 |
2. 本特集の趣旨
本プロジェクトは、前述のとおり全8回開催し、報告書の発行(2025年6月)をもって終了した。報告書には、各回の抄録のほか、参加者3名からの寄稿も掲載している(連合総研・松岡康司氏、富士社会教育センター・新妻健治氏、新川敏光氏)。本特集ではこれらのうち、本プロジェクトの主査を務められた新川氏の寄稿を掲載する。
新川氏の論稿「社会運動ユニオニズムの歴史的意義と今日的課題――アメリカ労働運動を事例として――」では、まず、今日のアメリカにおけるストライキの急増の状況を確認したうえで、その背景に富の集中と中間層の没落という格差の拡大があることが確認される。そして、このような抗議行動が一時的な不満の爆発にとどまらず、格差社会の構造的問題に抗する社会運動として展開するためには、労働組合がさまざまな社会運動と連帯し、社会的公正を求めることでその認知と評価を高めていくこと、すなわち社会運動ユニオニズムを推進することが重要だとする。
しかし、アメリカにおける社会運動ユニオニズムの実現には様々な障壁があるという。とくに、労働組合結成のハードルの高さ、および就労権(the right to work)の問題――「組合の従業員に対する干渉からの自由を保障する」という意味での「働く権利」であり、実質的には組合参加の誘因を弱め結成を困難にする―― が制度上の問題として指摘される。
また、アメリカの労働組合側の動きを見ても、社会運動ユニオニズムの実現が必ずしも容易でないことが推察される。それは具体的には、組合員の利益のみを追求するビジネス・ユニオニズムを全面的に打ち出したAFL(全国労働総同盟)にたいして批判的なスタンスをとる産別派が結成したCIO(産業別組織会議)が、組織的な混迷の末AFLとの合併に至る歴史や、移民労働者の組織化をはじめとする社会運動ユニオニズムを展開したSEIU(サービス従業員国際組合)などの組織が勝利のための変革連合(Change to Win Coalition)を結成したものの、ビジョンの欠如により運動が持続せず、全組織がAFL-CIOに復帰していったという顛末に見て取ることができる。これらの事例はいずれも、ビジネス・ユニオニズムを標榜する組織のなかから社会運動ユニオニズムへ向けた動きが起こったとしても、それらが十分な持続力をもたず、もとの体制に再統合されてしまうことが珍しくないことを示唆する。
しかし、新川氏は、このような歴史上の事例をもって社会運動ユニオニズム自体を実現し得ないものと見なすのは早計であると論じる。現在の経済社会の変化を所与とするならば、労働運動のとるべき道は、ビジネス・ユニオニズムへの回帰ではなく、社会運動ユニオニズムの「刷新」であるというのが新川氏の主張である。その「刷新」のために重要になるのが、「構築されるものとしての階級」という視点である。「市民」や「国民」ではなくなぜ「階級」なのか。働く者のあいだでも労働環境や生活環境が同質的ではあり得ない現代において、「階級」が生まれることはいかにして可能か―― 歴史と国際比較の両方にまたがる経験的研究と、理論的研究を積み重ねられてきた新川氏の考察を、ぜひ本文でお読みいただきたい。この論稿ではアメリカの動きが事例として取り上げられているものの、社会運動ユニオニズムの「刷新」と「階級」の構築という課題の指摘は、日本の労働運動にたいしても警鐘を鳴らすものと言える。
なお、新川氏は、長きにわたって当研究所の理事も務められたが、本研究プロジェクトの完了、および本年(2025年)の総会をもって退任された。この場を借りて、新川氏の長年のご尽力に改めて深謝の念を表したい。